『三輪山をしかも隠すか雲だにも情あらなぬ隠さふべしや』額田王(巻一・十八)
我々はこの歌に、万葉時代の典型的な美学・事情を見出すことができる。
この歌を詠んだ額田王に関しての詳しい資料は何も残っていないが、
名前から当時の王族、若しくはそれに準ずる身分の女性であったことは分かる。
これは、自身で詠った長歌への反歌。
奈良の三輪山の美しい輪郭を遮る雲に対して、あたかも人に対してのように、
意味のない祈りを捧げるという姿はなんと叙情に溢れた、美しい姿を想像させるのだろう。
三輪山の向こうには己の愛しい人でもいて、その人に対しての恋情を詠わずにはいられなかった、
旅路の女性、という景色が脳裏に浮かんでくるかのようだ。
しかし、本当はそんな美しいものだけではない。
この歌は、大和から近江への遷都が実行された時に額田王が詠んだものである。
三輪山を隠す雲は、自然の抵抗であり、怒りであろう。
三輪山は、今まで暮らしていた思い出深い大和の地を象徴している。
額田王は、遷都により離れなければならなくなった大和の地を惜しんでこの歌を詠んだのである。
惜しむ心だけではなかったのかもしれない。
遷都をするのだから見知らぬ土地での生活への不安は拭い去れなかったであろう。
額田王は、遷都に対して反対だったのかもしれない。
その気持ちを、三輪山に雲がかかる、という表現にして、ささやかな抵抗を試みたとも考えることができる。
万葉集の詠まれた時代は、権力者たちの強い力が存在していた。
反体制的なことを詠うことが叶わないが、人の心は常にどこかへ発散されるものである。
それはこの歌のように、表向きには詠われないが、必ずどこかに潜んでいた。
抑えられた分、その思いは激しい情熱となり、己を振るわせる感動となっているのである。
愛しい三輪山(大和)を隠してしまう雲(支配者である天智天皇)よ、思いやりも必要だ、
隠してはならぬ、隠してならないものなのだ、と心の中で強く反発する額田王が易々と想像できる。
そこには権力者へのささやかな抵抗と、一方では決まった遷都を受け入れつつも、
しかし大和を惜しむ心が同居していて、なんとも複雑である。
この複雑さと、表向きの旅情と慕情が混合し、なんとも独自の世界を創り上げている。
全体的には現実から抜け出たような寂しさが「もののあはれ」の世界であり、
ほんの一握りの有閑貴族たち特有の美学がよく現れている。
このような表向きの儚さと、時代に押し殺された本音が万葉集の根底に流れるものである。
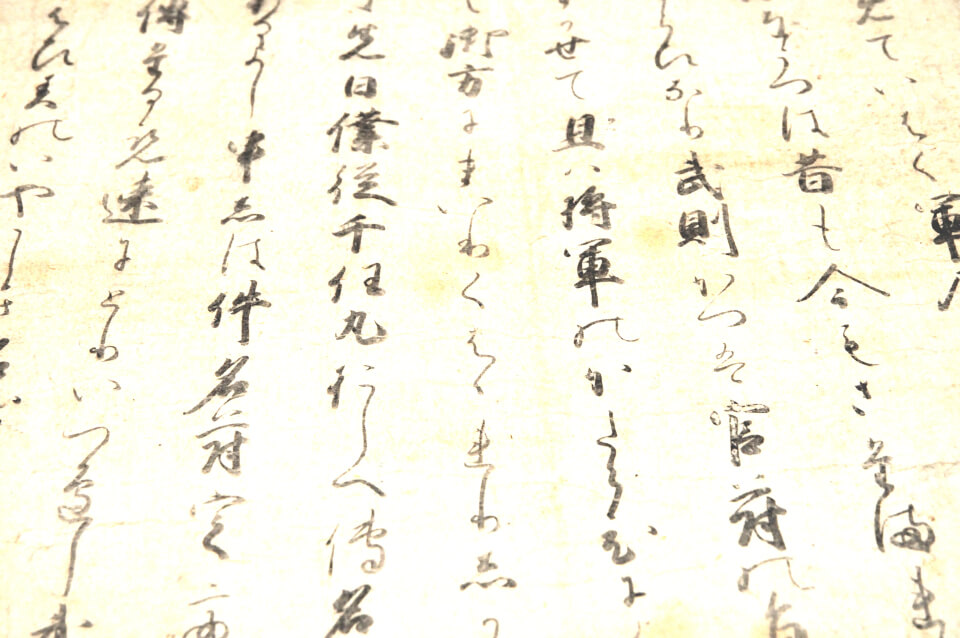
また、歌には様々な使われ方があった。例えば、次のような歌がある。
『千万の軍なりとも言挙せず取りて来ぬべき男とぞ念ふ』高橋虫麿(巻六・九七二)
言葉だけを読めば、なんと勇ましい歌であろうか。
色々事情があるだろうが、黙って敵の大軍を撃退してくることが男だと、これから戦場に赴く相手を称える姿が思い浮かぶ。
勇ましい中身とは裏腹に、なんとも美しい言葉の連なり、そして最後を濁さずはっきりと締めくくったこの歌は、
裏の事情を思いやるかすかな「もののあはれ」を匂わせつつ、しかし勇敢な男らしい歌である。
そうはいえども、もちろんそれだけでは完結しないのがこの当時の歌である。
これは、歌を詠うぐらいでしか己の存在を誇示できなかった歌人虫麿が、
絶対権力者藤原不比等の三男で、軍事責任者という重任として赴任する藤原宇合に対して捧げたいわばご機嫌取りの歌である。
お世辞の歌と分かれば歌の魅力も色あせそうなものだが、
そうではないのは歌自体の勇ましくも美しい響きによるものであろう。
このような使い方をされる歌もあったのだ。
万葉集にはこの二例のように本音と建前が混在する歌が多いが、そうではない例もある。
『験なき物を思はずは一坏の濁れる酒を飲むべくあるらし』大伴旅人(巻三・三三八)
この歌自身には全く裏がない。
歌からは豪傑が酒を飲みながら高笑いをする様が浮かんでくるようだ。
歌という高尚な形態をとっているが、「一坏の」「濁れる」などという言葉を選んだ様には、
素朴な人間性が窺われるようだ。どこまでも真っ直ぐな歌である。
歌自身に表しかなくとも、この歌い手の人生を知ると歌の意味は一変する。
大伴という名家の家長として一時は大納言の位にまで出世したのが大伴旅人である。
だが、藤原氏の台頭により太宰府へ左遷され、また大宰府では愛妻を亡くし、恵まれない晩年を送った。
そういう人生を経てきた旅人が詠んだ歌である。
「験なき物」には藤原氏への嫉妬や羨望、憎しみもあろう。
落ちぶれてしまった大伴家に対する想いもあろう。
また、長年連れ添った妻に対する個人的な気持ちもあろう。
そういったことを乗り越えて、一坏の濁り酒を飲むことの楽しみを詠った旅人の気持ちを想うと胸に響くものがある。
歌の言葉を詠んで分かる思いではなく、歌い手の名前の人生を知って始めて分かる思いである。
また、いかに高い身分の人間だろうとも、人間である限り悩みも楽しみも同じだ、という教訓が読み取れるかのようだ。
このように、万葉集には歌自体から真意が読み取れないものもある。
だが、一歩突っ込んで調べてみると、それぞれの歌に意味があり、その意味は現代に生きる私たちにも強く響いてくるものである。
これが、時代を超えても色褪せない万葉集の魅力であろう。